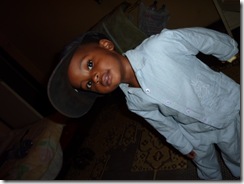学生気分も完全に抜けきったと言えるのか定かでないのに(第一、半年前までまた学生やってましたし…)、私もいわゆるアラフォーの仲間入りをしていることに気付きました。(いまさら?)
同年代の人たちを一括りにしようとする世代論ってあまり好きじゃないけど、上とも下とも世代の差を意識せざるを得ないちょっと微妙な年齢になってきていることは、最近徐々に感じます。
まだまだ若いつもりだけど、自分が以前は「おじさん」と一括りに捉えていた年齢帯に突入しつつあります。そういえば、白髪も増え、しわも出てきて、体が無理をきいてくれなくなり始め。。
どう足掻いても歳には逆らえませんし、現実逃避しても何の役にも立たないので、開き直って「アラフォーにもなれば、こうありたい」という心得=自戒を、考えつくまま列挙してみました。
- 「最近の若いもんはよく分からない」とか言うべからず: 自分が同じことを言われていたのも、そんなに昔じゃない。よく分からないのは、分かろうとする努力が足りないから。若いもんから吸収できること、しなきゃいけないことはまだまだあるはず。
- 若いもんに媚びるべからず: アラフォーになるまで、真摯に経験と知見を積み、思索と省察を重ねて来ていれば、自分が学生の頃に考えていたことと今考えていることの間に距離が生まれているのは、極めて自然なこと。同様に、今の学生が考えていることとの間にも、距離があって当然で、そうでなければおかしいくらい。若いもんに「かっこいい」と思われたい気持ちも分かるけど、迎合するのはみっともない。今の自分に自信を持ち、かっこ悪く見えることも、退屈に聞こえることも、堂々と主張し、やり通そう。
- 目上は敬して之を遠ざけるべからず: 若い頃は、目上の人を必要以上に軽んじたり、うざったがったりしがち。経験の大切さを真に身に沁みては理解していなかったし、また年輩の人にどう接すれば良いのか今ひとつよく分からなかったから、それもある意味仕方なかった。でもアラフォーにもなれば、そんな言い訳は通用しない。彼らの経験の蓄積とそこから生まれる洞察に敬意を払い、積極的に学ばせてもらおう。
- 目上を「上から目線」で見る姿勢を持つべし: アラフォーたるもの、何も分からずに上に楯突いて無責任にえらそーな事言ったり、逆に上から言われたからとよく考えもせず従ったり、といったことはいい加減卒業しないとまずい。会社の重役であれ一国の大臣であれ、どんな目上の人に対しても、自分自身が当事者になったつもり、さらには彼らの上司にでもなったつもりくらいの意識を持って考え、建設的なアドバイスができるようになる必要がある。そうすることで、大局を見て必要に応じ優先順位をつけ、個別の正論に従うのではなく全体最適を図ることができるリーダーとしての素養を培おう。
- 愛する者を愛すべし: 若い頃は自己愛が偏って大きく、他を本当の意味で愛する余裕のない人が多い。家族でもいい。恋人でも友人でもペットでもいい。「神」や、世界中の生きとし生けるものと言うならそれでもいい。自分自身にしっかり愛情を注いであげるのも大事だけど、自分以外に心底から愛することができる対象がいるというのは、かけがえのない幸福。その愛情を伝え、育む努力を決して怠ってはいけない。
- 守りに入るべからず: 守るべきものがあるのは素晴らしいこと。だけど、守りに専念するにはあまりに早すぎる。これまでに築いてきた関係、信用などの資産を、守るだけでなく、動かし、組み替え、工夫して最大限に活用して、さらなる高みを目指そう。
- スタンスを取るべし: ケロッグでグループディスカッションをしていた時に、私が「Xじゃないかなと思うんだけど、でも皆がYと考えるのも分かるんだよね」みたいな発言をしたところ、すぐさま友人から「スタンスを取れ」とビシッと言われた。「議論を深め、グループとしてより良い結論に到達するために、異なった視点から(例え100%確信がないとしても)きっちり論理を展開して見せろ」ということ。自分の主張が合ってるか間違ってるか、採用されるかされないかよりも、その議論をすることが全体の結果の向上に役立つかどうかを、一番の基準とし、自分を捨て石にすることも厭わない。
- 敵をつくることを恐れるべからず: 不必要に敵をつくることは避けなくてはいけないけど、誰にでも好かれようとしていては、何事も成し遂げることはできない。凡そあらゆる変革には、得する人がいる一方で、損をする人もいる。本質を抉る発言であればあるほど、賛成する人も反対する人も多くなる。敵を味方に変える工夫はするが、しかし敵をつくることを恐れず腹を決め、主張すべきことは主張し、為すべきことを為そう。
- システムを動かすべし: 自分の力だけでは一人相撲。周囲の人の力を使っても、まだ狎れあいの域を出るのは難しい。若い頃はそれもいい。色々やってみてそこから学べばいい。ただ、対症療法でない本質的な持続的変革は、人の動静の根底にあるシステムを動かして初めて可能なことを、アラフォーにもなれば理解していなければならない。果敢という名の思考停止、挑戦という名の自己陶酔を脱却し、思考、行動、議論の全てを駆使してシステムを動かそう。
- 歴史に学ぶべし: 「愚者は経験に学び、賢者は歴史に学ぶ」。空虚な理念でなく、人間の現実を学ぶには、様々な社会の様々な歴史は最良の教科書。複雑な社会のダイナミクスを理解するのにも、この上なく貴重な「実験室」 を提供してくれる。目先のトレンドに振り回されていることに気付きもせず振り回されたり、せっかく歴史を紐解いたのに英雄崇拝に終始したりといったことは、アラサーまでで十分。現実を知らずして、現実を変えることなんてできない。歴史の深い教訓を学び、活かせるようになろう。
- バランスにしがみつくべからず: バランスは確かに重要。だけど、バランスをとること自体が究極の目的ではないことに、もう気付かなければならない。何でもかんでも「バランスが大事」という科白で片付けていたら、突き抜けることなんてできない。現状より高次のバランスに達するためには、今あるバランスも崩して前に進まなくては。人間は、直立している状態からバランスを崩して、初めて前に進むことができる。
- 「不惑」になるべからず: 孔子曰く、「四十而不惑」。でも、40といえばもうそろそろ一生の締めくくり方を考え始なければいけなかった孔子の時代と異なり、今のアラフォーはまさに人生これから。惑わなくては進歩は無い。前に進みつづけるために、大いに惑わずにはいられない状況にこれからも自分を置いていこう。
同年代のアラフォーの方々の、「これも大事!」という心得がありましたら、教えてくださいね。
また、アラフォー未満の方々の「アラフォーにはこうあって欲しい」という要望、元アラフォーの方々の「あの頃の自分にこう言ってやりたい」という教訓も、是非お聞きしたいです。
今日も応援クリック
ありがとうございます
ご感想をどうぞ!
- Yay = 良い/ 面白い/ 賛成
- Boo = 悪い/ つまらない/ 反対
- More on this = この話題についてもっと読みたい
- Difficult = 何だか難しくてよく分からない
- Yay = 良い/ 面白い/ 賛成
- Boo = 悪い/ つまらない/ 反対
- More on this = この話題についてもっと読みたい
- Difficult = 何だか難しくてよく分からない